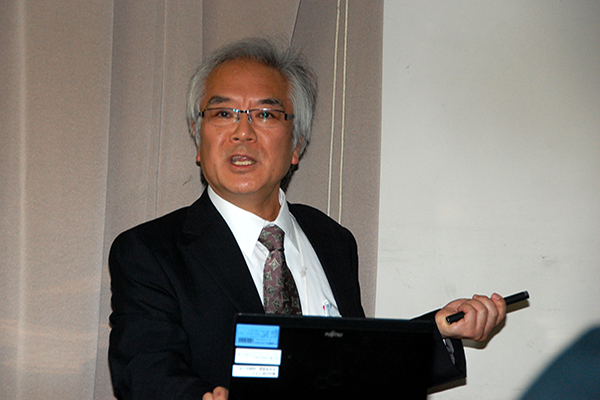防災関係各界の代表者等により、防災教育における各位の取組の紹介と“地域における防災教育の実践に関する手引き” “学校を核とした防災教育の推進”をテーマとした分科会を行いました。

○飯塚三陽 様
(命守会(命を守る防災教育を推進する会) 会長)
自然災害から大切な地域住民の命を守ることを目的に活動しており、大雨防災ワークショップでは、一方的に教えるのではなく気づきを大事にしていることや、学校の先生方が独自に実践できるようにマニュアルも作成した等をご紹介いただきました。

○鈴木介人 様
(八千代市立みどりが丘小学校 みどりサポートチーム代表)
311で避難所運営を学校の先生だけでやっていたのを見て、翌年から保護者として活動を始めており、今年消防庁から防災まちづくり大賞を受賞したことや、5年目の今年は防災教育のさらなる普及のため隣接の小学校で出前授業を行う等をご紹介いただきました。

○高橋教義 様
(仙台市立郡山小学校 校長)
2011年に東日本大震災に遭い、今までの防災教育をほかの学校のために活かしたいと、被災した学校に行っていることや、中学生が主導して防災教育を行うことをメインプランとし、班ごとに地域の核となる団体と連携して行っている等をご紹介いただきました。

○谷口一之 様
(糸魚川市立根知小学校 前校長)
全ての教育活動に防災教育活動を取り入れており、防災の視点を入れた特別活動の授業を実施し、運動会に"いきなり避難訓練"を実施した等をご紹介いただきました。

○山崎由紀子 様
(KUNIBO(くにたち地域外国人のための防災連絡会) 連絡係)
地域の中の外国人といかにコミュニケーションをとりながら、防災という難しいテーマについて学んでいただけるかについてご紹介をいただきました。

○谷本明 様
(田辺市立新庄中学校 教諭)
今年で16年目となる「新庄地震学」の活動内容と、自校だけではなく近隣中学校や地域住民へと活動の場を広げた活動についてご紹介いただきました。
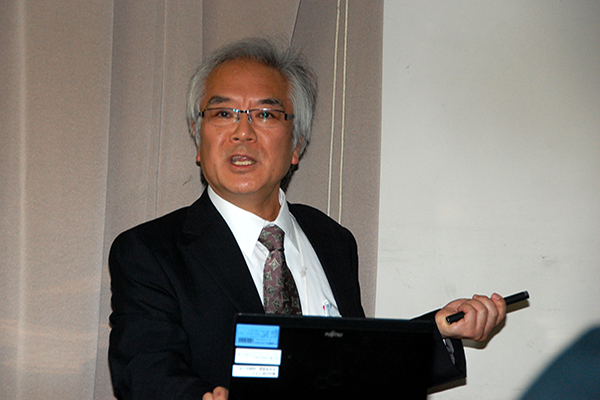
○花崎哲司 様
(香川県立盲学校 危機管理担当)
香川県立盲学校での防災教育チャレンジプランを通じての成果のみならず現状の課題もおりまぜながら、生徒だけでなく教師らの防災力を向上すること、地域住民を巻き込んでの防災教育の実践が必要であること等をご紹介いただきました。

○藤岡達也 様
(滋賀大学 教育学部 教授)
防災教育の推進には学校を核とした学内・学外のネットワークの形成が重要であること、日頃から自分の住む地域について学ぶことが、学内(教師、生徒)と学外(地域社会)のネットワーク造りにつながることなどのお話をいただきました。

○穂積誠 様
(千葉県 教育庁 教育振興部 学校安全保健課 指導主事)
防災教育に関する学校との連携について、県としての取組内容と課題について紹介いただき、防災教育に関して県内の防災に対する温度差を無くすため先進事例等を参考に防災教育に関する取組を進めたいとのお話をいただきました。

○吉門直子 様
(文部科学省 初等中等教育局 保健教育・食育課 安全教育調査官)
小・中学校で行われている避難訓練(緊急地震速報の活用、告知無しで実施等)の事例や、一般教科(社会科や理科等)における防災教育の取り組み事例についてご紹介いただきました。
○意見交換会
各パネリストの活動紹介後、実行委員のコーディネートで各分科会のテーマについて意見交換を行いました。その後質疑応答も行われ、それぞれ終始活発な意見が飛び交う場となりました。
「地域における防災教育の実践に関する手引き」についての分科会
- 支援学級の生徒の防災訓練について
- 地域の方々との防災意識への温度差 等

「学校を核とした防災教育の推進」についての分科会
- 防災教育を受けた生徒たちが生涯を通じて防災に携われる環境づくり
- 高等学校と小・中学校(義務教育)の防災教育の連携について
- 被災地と被災地外での防災意識への温度差解消について 等

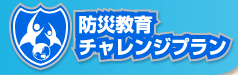
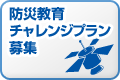
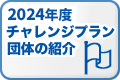
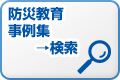
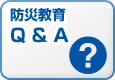
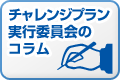
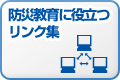

 廣瀬昌由様(内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当))より、「悩んでいる点などあるかと思うが、意見交換によってさらにレベルアップしてほしい。今日の取り組みも、これから社会の中で実践されていき、活動が地域の核になる、いろいろな場面で地域に貢献されると思いますので、私どもも一緒に支援させていただきたい。」とご挨拶をいただきました。
廣瀬昌由様(内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当))より、「悩んでいる点などあるかと思うが、意見交換によってさらにレベルアップしてほしい。今日の取り組みも、これから社会の中で実践されていき、活動が地域の核になる、いろいろな場面で地域に貢献されると思いますので、私どもも一緒に支援させていただきたい。」とご挨拶をいただきました。
 また、井上浩一委員(防災ネットワークプラン 代表)からは、各実践団体の発表・取組内容に対して、団体ごとに良い点や今後の課題について総括のコメントをいただきました。
また、井上浩一委員(防災ネットワークプラン 代表)からは、各実践団体の発表・取組内容に対して、団体ごとに良い点や今後の課題について総括のコメントをいただきました。


 趣旨説明では、林春男委員長(国立研究開発法人防災科学技術研究所 理事長)より、「様々な防災教育にかかわる皆さまが一堂に会する場をつくろうと10年ほど実施しており、昨年の仙台の防災会議を一区切りとして防災教育の実践の手引きを内閣府と作成した。次は、防災教育を体系化していく10年ではないかと考えている。」「今年から文科省で防災教育の所管が初等教育局に移り、防災教育が変わるきっかけとなることを期待しているが、学校の中だけで実践することは難しいため、『学校を核とした防災教育の推進』をテーマとした。今初等教育にどのように防災教育を取り込んでいくのか、防災教育のユニバーサルデザイン化が重要なことだと考えており、こういうことについて議論を進めていきたい。」とご挨拶をいただきました。
趣旨説明では、林春男委員長(国立研究開発法人防災科学技術研究所 理事長)より、「様々な防災教育にかかわる皆さまが一堂に会する場をつくろうと10年ほど実施しており、昨年の仙台の防災会議を一区切りとして防災教育の実践の手引きを内閣府と作成した。次は、防災教育を体系化していく10年ではないかと考えている。」「今年から文科省で防災教育の所管が初等教育局に移り、防災教育が変わるきっかけとなることを期待しているが、学校の中だけで実践することは難しいため、『学校を核とした防災教育の推進』をテーマとした。今初等教育にどのように防災教育を取り込んでいくのか、防災教育のユニバーサルデザイン化が重要なことだと考えており、こういうことについて議論を進めていきたい。」とご挨拶をいただきました。
 森本輝様(内閣府政策統括官(防災担当)付企画官(調査・企画担当))より、「熊本地震の経験で、地域の防災力の強さは災害復旧復興にも直結してくるところであり、事前にしっかり備えておくこと、地域がつながっておくことが重要ということを感じた。浸透させていくためのツールは、こういう防災教育を地道に地域で進めていただける取り組みと両輪となって進めていかないと地域に浸透していかないと思っている。いろいろなご意見をいただいて、知見を得るためのヒントにしていただければと考えている。」とご挨拶をいただきました。
森本輝様(内閣府政策統括官(防災担当)付企画官(調査・企画担当))より、「熊本地震の経験で、地域の防災力の強さは災害復旧復興にも直結してくるところであり、事前にしっかり備えておくこと、地域がつながっておくことが重要ということを感じた。浸透させていくためのツールは、こういう防災教育を地道に地域で進めていただける取り組みと両輪となって進めていかないと地域に浸透していかないと思っている。いろいろなご意見をいただいて、知見を得るためのヒントにしていただければと考えている。」とご挨拶をいただきました。
 『学校防災の今後の展開』をテーマにご講演をいただき、「学校における安全の取り組みは、安全教育と安全管理で成り立っており、それをつなぐものとして組織活動がある。これらを進めるためには、各教職員が協力体制をつくり、地域社会と連携するための組織活動をしっかりとさせていなければならない。」「学校安全の推進に関する国の計画は、安全教育・管理それぞれで充実をさせて、総合的かつ効果的な安全の取り組みを実施するとしており、危機管理マニュアルの作成や訓練等を行っている。」「児童の安全を預かっていることを認識して、防災教育を各省庁と進めていきたいと思っている。」などのお話をいただきました。
『学校防災の今後の展開』をテーマにご講演をいただき、「学校における安全の取り組みは、安全教育と安全管理で成り立っており、それをつなぐものとして組織活動がある。これらを進めるためには、各教職員が協力体制をつくり、地域社会と連携するための組織活動をしっかりとさせていなければならない。」「学校安全の推進に関する国の計画は、安全教育・管理それぞれで充実をさせて、総合的かつ効果的な安全の取り組みを実施するとしており、危機管理マニュアルの作成や訓練等を行っている。」「児童の安全を預かっていることを認識して、防災教育を各省庁と進めていきたいと思っている。」などのお話をいただきました。
 『熊本地震を教訓とした防災教育』をテーマにご講演をいただき、「今年、熊本で起きた地震の大きな特徴は、益城町で震度7が28時間の間に2度街を襲ったことである。地震学的になぜこのような地震が起きたかしばらくは分からなかった。」「地震というのは比較的同じ場所で繰り返し起こり、過去にも大きな地震が起きているが、それでも九州では地震が起きないと考えた人がいたことは衝撃的だった。国の地震調査研究推進本部では、布田川断層帯の地震発生確率を0%〜0.9%くらいと評価しており、これはやや高いグループに属するが、一般の人は地震が起きないと受け取ってしまうため、どう伝えるべきかよく考える必要がある。」「熊本で起きたようなことは日本中どこでも起きる可能性があることが一番重要なメッセージで、日頃からきちんとした防災教育を行い訓練をしておく必要がある。」などのお話をいただきました。
『熊本地震を教訓とした防災教育』をテーマにご講演をいただき、「今年、熊本で起きた地震の大きな特徴は、益城町で震度7が28時間の間に2度街を襲ったことである。地震学的になぜこのような地震が起きたかしばらくは分からなかった。」「地震というのは比較的同じ場所で繰り返し起こり、過去にも大きな地震が起きているが、それでも九州では地震が起きないと考えた人がいたことは衝撃的だった。国の地震調査研究推進本部では、布田川断層帯の地震発生確率を0%〜0.9%くらいと評価しており、これはやや高いグループに属するが、一般の人は地震が起きないと受け取ってしまうため、どう伝えるべきかよく考える必要がある。」「熊本で起きたようなことは日本中どこでも起きる可能性があることが一番重要なメッセージで、日頃からきちんとした防災教育を行い訓練をしておく必要がある。」などのお話をいただきました。
 『地域と連携したこれからの学校防災』をテーマにご講演をいただき、「『防災教育をめぐる活動』、『学校を取り巻く地域と活動』、『教育課程:学力向上と防災教育』、『地域と連動した災害事例の取り組み』、『持続可能な学校防災』について」「学校は、学習指導要領にのっとり地域防災計画と連動することもあり、改めて地域と学校で、防災教育を核とした今後新たな連動を期待したい。」などのお話をいただきました。
『地域と連携したこれからの学校防災』をテーマにご講演をいただき、「『防災教育をめぐる活動』、『学校を取り巻く地域と活動』、『教育課程:学力向上と防災教育』、『地域と連動した災害事例の取り組み』、『持続可能な学校防災』について」「学校は、学習指導要領にのっとり地域防災計画と連動することもあり、改めて地域と学校で、防災教育を核とした今後新たな連動を期待したい。」などのお話をいただきました。